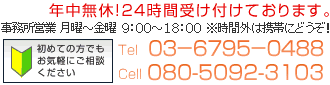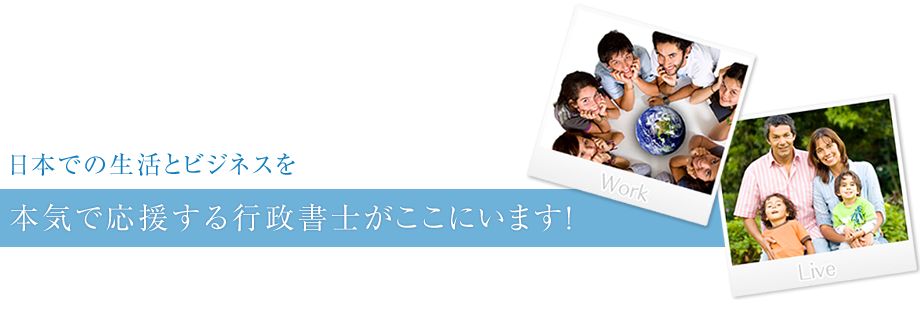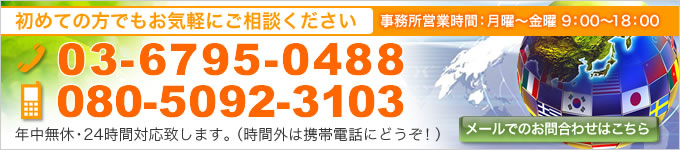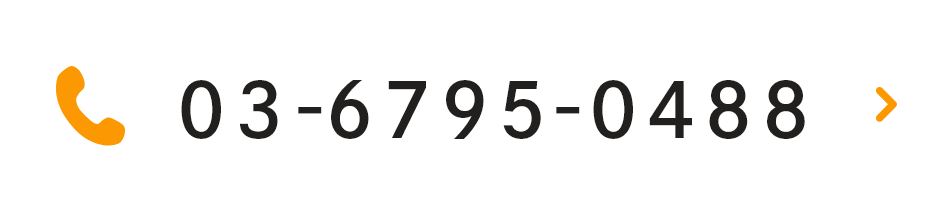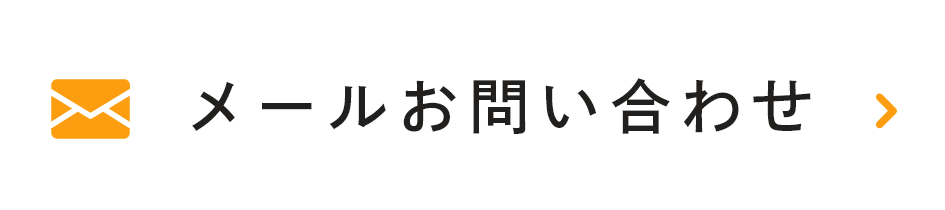ブログ
2019年10月15日 火曜日
名前だけは知っていた
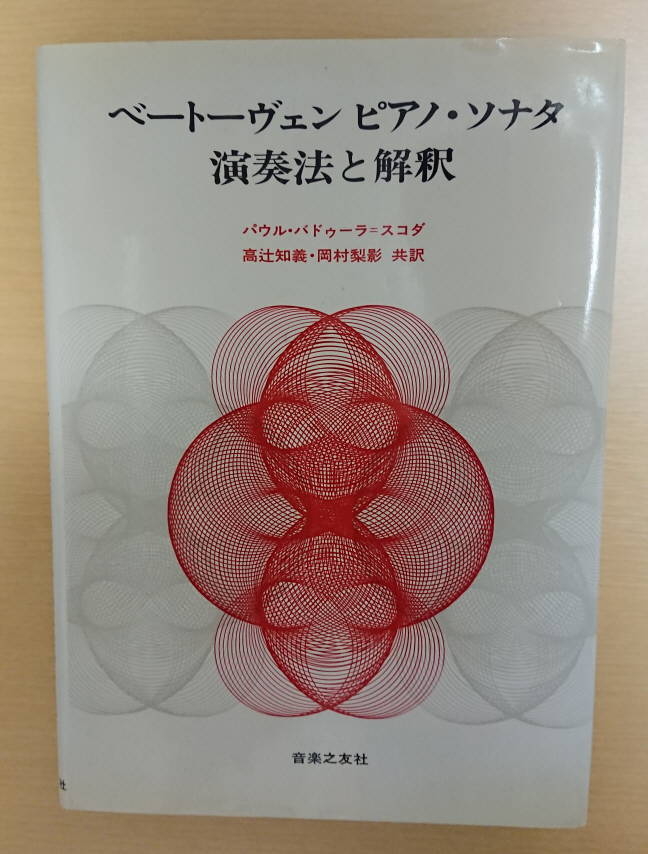
パウル・バドゥラ・スコダの公演中止という告知をたまたまネットで目にしました。
名前はよく知っているけど誰だっけ?・・と思ったんです。
ピアニストなのは分かりますが、この人のCDを持っているわけでもなく演奏を聴いた覚えもありません。顔すら知らないのです。
で、名前だけ良く知っているのは何故だろうと考える必要があったのですが、すぐに思い出しました。
「ベートーヴェンピアノソナタ演奏法と解釈」という本を書いた人でした。私、この本けっこう読んでたんです。著者として覚えていたんですね。
この10月に来日予定でしたが、先月亡くなられたようです。92歳で現役って凄いです。
投稿者 | 記事URL
2019年9月4日 水曜日
簡易帰化
白鵬関が日本国籍を取得した(帰化した)というニュースが流れました。
普通に考えて、白鵬のような人は確実に日本国籍が取得できます。配偶者が日本人ですから簡易帰化と言われます。その他にも収入大、国技における功績大、そして名声など、犯罪者にでもならなければ拒否する理由がありません。申請してから許可されるまで早かったそうですが、それも当然でしょう、
とは言っても、提出する書類等が少なかったわけではなく、一応、一般外国人の帰化申請と同じだけの書類を出したはずで、申請要件や審査が緩くなるのが簡易帰化です。
帰化申請は、集める書類も作成する書類も非常に多いですから、私の場合、正直なところ・・依頼が入ってもそれほど嬉しくないんですよね。報酬額に対する仕事量が多い気がするので。でも頼まれたら仕事と割り切ってやってます。報酬額もっと上げようかなぁ
投稿者 | 記事URL
2019年8月25日 日曜日
リラックスタイム

この3~4日間、急に風邪をひいてしまってちょっと無理してました。今日は日曜なのでお客さまからの電話もないだろうし、リラックスして音楽とか聴いてました。
音楽のリスニングスタイルは時代とともにどんどん変わってきましたが、最近はまたレコードにもスポットがあたり、大手家電店に行けばレコードプレーヤーを載せたた高級オーディオががあったりして、レコード世代の私としては懐かしい匂いを案じることができます。しかしまあ、今からオーディオに凝る気はないので雰囲気を味わうだけです。
私も中学生の頃はレコードを聴くためにソコソコのオーディオセットが欲しくてアルバイトをしたものです。田舎でしたから大音量も大丈夫でした。
上京してからCDの時代になって、それに合わせるようにミニコンポが主流となり。カセットテープやCDのウォークマンが登場してイヤホン型のヘッドホンで外出時に聴くのも普通になりました。さらに音楽もデータとして販売されるようになって小さなマイクロSDに膨大な曲を入れて持ち運べる時代です。ほんで音質がどうとかでハイレゾ音源とか言い出してます。実は今まで売りまくってたCDの音は悪かったという話。CDの規格を決めるときに人には聞こえない音域はデータに乗らなくて大丈夫だと技術書たちは判断してCDのデータ規格を決めたんでしょう? CDに入る時間はカラヤンが第9が収録できる長さといったからそうなったというけど、カラヤンはその音質に納得したんでしょうか。ちょっと訊いてみたい。
話は戻りますが、私も最近までスマホやウォークマンにイヤホンでしたが、すぐに耳が痒くなってしまうので、今ではもっぱらアンプ内蔵型のスピーカーをつないで聴いています。安い物ですが、狭い部屋ではいい音してます。(もちろん左側にももう1コあります)
投稿者 | 記事URL
2019年7月22日 月曜日
永住申請提出資料
今月(7月)から永住申請の提出資料が増えています。
基本的な提出資料として、ねんきん定期便など年金関係のものと諸々の税金の滞納が無いことの証明書が明記されました。
6月までに申請した方についても、審査の過程でそれらの資料を要求されることもあるとかないとか。そういうことを6月以前に申請したお客様にも一応連絡しながら、だったらもっと早く7月からこうなりますってアナウンスが欲しかったと思うところです。とは言っても、永住申請にも申請人の状況(カテゴリというか)によって提出する資料が若干異なっており、確かに一部のカテゴリの申請対象者には6月以前からその記載があったのですが、同じ日に全てのカテゴリを確認してその記載の無いカテゴリの人は従来通りだと私が勝手に思い込んでいたというのもあるんです。おそらく記載を順次直している過程で確認したのでしょう。というわけで、何かの変わり目にはこまめに注意深く確認しながら進めなければならないなと反省した次第です。ん、私の確認が甘かったという結論になってしまいました。消そうかな・・
投稿者 | 記事URL
2019年6月22日 土曜日
夜コーヒーを飲むと

私、夜コーヒーを飲むと眠れなくなるので、だいたい午後4過ぎたらコーヒーを飲まないようにしています。
木曜の夜に錦糸町でビザ取得の相談のためスタバに入り、飲み物は何がいいか?ということで、炭酸であれば何でもいいと言ったところ、コーラのようなものをもってきてくれました。それはコーヒー味の炭酸で、なかなかスッキリして旨かったのですが、時間が夜の10過ぎ。帰って床についても、目が冴えてしまって一晩中眠りにつくことができませんでした・・・
錦糸町からの帰りに見たスカイツリーは涼し気な色をしてました。
投稿者 | 記事URL
2019年6月9日 日曜日
永住と帰化
永住者の国籍について誤解されている日本人が意外と多いように思います。
私の知人にも「永住者=日本国籍」と思っている方がいます(誤解のまま放置中)。
それは置いといて・・
外国人のお客様から、帰化すると何かいいのか?、永住者が帰化するメリットは何か?
と質問されることがあります。
1.世界最強のパスポートがもてる。
2.自分の公的証明書が日本国内で調達できるようになる(たぶん)。
3.うっかり再入国期間を過ぎて在留資格を失う心配が無い。
私が思いつくのはその3つくらいでしょうか・・
実際に帰化申請する人にとっては、メリット・デメリットだのを抜きに気持ちの問題が重大でしょう。
母国の国籍を離脱しても日本人になりたいという気持ち。そうなるのは途上国出身者が多数になるのは仕方がありません。
投稿者 | 記事URL
2019年5月27日 月曜日
DAP(ダップ)
 スマホで音楽をきいていると電話がかかってきてビクっとしたりバッテリーの消耗が早いので専用のプレーヤーを買いました。安いのになかなかのものです。
スマホで音楽をきいていると電話がかかってきてビクっとしたりバッテリーの消耗が早いので専用のプレーヤーを買いました。安いのになかなかのものです。デジタル・オーディオ・プレーヤー を略してDAP(ダップ)だそうです。
投稿者 | 記事URL
2019年2月28日 木曜日
一方通行です
ほとんど知人の方々ですが、意外とこのブログを見てくれている方がいるんです。
先日、読んでくれている知人から、もっと仕事関係でちょっと専門的な感じのことも書いたほうがいいじゃない?、というご指摘がありました、
確かに、もともとはこのHPが検索にヒットしやくするためのものですから、もっと仕事に絡めた内容で検索されやすそうなワードを多用して情報発信的なものを書くべきなのですが、どうもそういうのは私の性にあいません。
いや、やろうと思えばできますよ。実務書や情報誌から拾ったことを形を変えて書けばいいだけですから簡単なことです。実際そうしている人も沢山いるでしょう。しかし、なぜかネットに書かれている情報は、専門の方が書いているにも関わらず肝心なことが間違っていることが多いのです。
私は駆け出しの頃、専門の方がネットに書いたことを信じて手続きを進めて失敗した経験がありますし(大した失敗ではなかったのでフォローはできましたが)、最近ですが、同業の方が同じように失敗して、その同業者は解任されて私に代役の依頼があったりしました。
そんなこともあり、実務経験で得た知識やノウハウでない限り、無理矢理な情報発信は信用ならないものになりかねませんし、そういうのを書いている人々と同じにはなりたくないという気持ちです。
私のお客様の中には、このブログで人柄がわかったから連絡したと言ってくださる方もいらっしゃいますので、まあ、これからもこんな感じでいこうと思います。
なお、トラックバックや返信は許可していませんし「いいね」もない、完全一方通行で書かせてもらっていますので、そこは悪しからず。
投稿者 | 記事URL
カテゴリ一覧
- 所長ブログ (76)
月別アーカイブ
- 2022年9月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (2)
- 2018年8月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (1)
- 2012年8月 (1)
- 2012年7月 (2)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (8)
- 2012年2月 (2)
- 2012年1月 (2)
- 2011年12月 (2)
- 2011年11月 (2)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (6)
- 2011年6月 (6)
- 2011年5月 (4)
- 2011年4月 (15)
- 2011年3月 (12)